中国経済は回復できるのか(1)習近平の「新質生産力」はなぜダメな政策なのか
習近平が打ち出した不況脱出策は「新質生産力」をスローガンとする経済刺激策で、一時的に中国株を上昇させたが、すでに多くの疑問や否定的見解が出ている。ひたすら新しい技術分野を拡大するという政策が、なぜ十分な効果を生まないか。それは経済というものを構造的に全体で見れば分かるはずだが、習近平はそうする気はなさそうである。
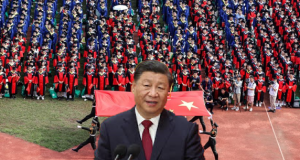 英経済誌ジ・エコノミスト4月4日号は「不況脱出のための習近平によるプランは間違っている」を掲載して、派手なプランの見かけとは裏腹に、実際には見当違いの政策であり、うまく機能しないことを3つの視点から指摘している。まず、消費者を無視していること。次に、国内の需要がないため輸出に頼ることになるが、それは困難であること。そして、習近平は起業家というものが分かっていないことである。
英経済誌ジ・エコノミスト4月4日号は「不況脱出のための習近平によるプランは間違っている」を掲載して、派手なプランの見かけとは裏腹に、実際には見当違いの政策であり、うまく機能しないことを3つの視点から指摘している。まず、消費者を無視していること。次に、国内の需要がないため輸出に頼ることになるが、それは困難であること。そして、習近平は起業家というものが分かっていないことである。
まず、どのようなプランなのか、簡単に見ておこう。「習近平は先端製造業を加速させることで国家のパワーを増大させ、高い生産性のある仕事を拡大することによって、中国経済を自己充足型に変化させ、アメリカの圧力に抗する力をつける」のが狙いだという。「そのため中国は、これまでの鉄鋼や高層ビルを製造建設する時代から、電気自動、バッテリー、バイオ産業、そしてドローン流通が中心の経済の黄金時代に飛躍する」のだという。
 その規模は「溜息が出るほどのもので」、この新質生産力プランは1年間の投資が1兆6000億ドルにも達する。それはアメリカの2023年総投資の43%に相当し、いくつかの産業において2023年との比較で75%もの上昇が見込まれているという。しかし、そんなことが可能なのだろうか。同誌によれば「これは基本的に間違ったプランといえる」。そこには先述した3つの決定的な錯誤が見られるからである。
その規模は「溜息が出るほどのもので」、この新質生産力プランは1年間の投資が1兆6000億ドルにも達する。それはアメリカの2023年総投資の43%に相当し、いくつかの産業において2023年との比較で75%もの上昇が見込まれているという。しかし、そんなことが可能なのだろうか。同誌によれば「これは基本的に間違ったプランといえる」。そこには先述した3つの決定的な錯誤が見られるからである。
第一にあげられた錯誤は「消費者の無視」であり、新質生産力プランが実行されたとしても、中国国内は単に不動産業を縮小させる方向へと向うだけだという。それは新しいハイテク製品が登場しても、中国の個人消費はGDPのたった37%に過ぎないため、国内だけの消費では成長牽引にはならないからだ。中国の国内の個人消費がいかに少ないかは、日本ですらGDPの60%ほどあり、アメリカは70%弱であることからも分かる。
 不動産業の停滞のなかで消費を維持し、さらに拡大していくには、もっと刺激策が必要であり、貯蓄率を引き下げて消費に向かわせるには、社会保障とヘルスケア制度を整え、都市に住む移民への市民サービスを開放する必要がある。ところが、習近平はこうした制度改革には乗り気ではなく、不動産バブル崩壊に対しての救済策も嫌っている。これでは当面の消費が伸びるのは無理だろう。
不動産業の停滞のなかで消費を維持し、さらに拡大していくには、もっと刺激策が必要であり、貯蓄率を引き下げて消費に向かわせるには、社会保障とヘルスケア制度を整え、都市に住む移民への市民サービスを開放する必要がある。ところが、習近平はこうした制度改革には乗り気ではなく、不動産バブル崩壊に対しての救済策も嫌っている。これでは当面の消費が伸びるのは無理だろう。
錯誤の第二は、いまも国内充足的な経済が可能だと思っている点で、実際には国内需要が弱くなっているのだから、新質生産力プランで生まれる新製品は、輸出しなければならなくなってしまう。そもそも、世界が2000年代の自由貿易を見直さざるを得なくなったのは、部分的には中国が展開した重商主義(ともかく外貨を稼ぐことに徹する貿易姿勢)に影響されたからだった。
 中国はアメリカやヨーロッパが中国に対して輸入制限をするならば、グローバル・サウスへの輸出を検討していると公言している。しかし、中国が新興国に対して輸出攻勢をかけたとしたら、それらの国ぐにの産業発展はどうなるだろうか。いまですら中国は世界の製造業の31%を占めているといわれる。その国がさらに新興国への輸出加速を考えているというのは、一種のブラックユーモアといってよいだろう。
中国はアメリカやヨーロッパが中国に対して輸入制限をするならば、グローバル・サウスへの輸出を検討していると公言している。しかし、中国が新興国に対して輸出攻勢をかけたとしたら、それらの国ぐにの産業発展はどうなるだろうか。いまですら中国は世界の製造業の31%を占めているといわれる。その国がさらに新興国への輸出加速を考えているというのは、一種のブラックユーモアといってよいだろう。
第三の間違いは「習近平という人が抱いている起業家への誤った見方」そのものであるという。この30年間にわたって、世界の産業を引っ張ってきたのは起業家だったが、習近平は彼らの産業における役割を無視したようなルールを作り、また、彼らをパージし、拘束するようなことを続けている。中国の株式市場もこの25年間は低調になり、外国企業は神経質になっていて、キャピタルフライトの兆候すら見られるようになっている。
 「中国はいま1990年代の日本になるかもしれないといわれている。つまり、デフレーションの罠にはまり、不動産バブルの崩壊に悩んでいる。さらに悪いことには、中国の場合には自国中心のモデルの一方的な押し付けが、世界貿易を後退させるかもしれない。もし、そうであるなら、地政学的な緊張が生まれてもおかしくない。アメリカとその同盟国はそうなることを望んではいないが、もし、中国が不況に悩んで国内に不満が充満すれば、繁栄していたころに比べてずっと好戦的になるかもしれない」
「中国はいま1990年代の日本になるかもしれないといわれている。つまり、デフレーションの罠にはまり、不動産バブルの崩壊に悩んでいる。さらに悪いことには、中国の場合には自国中心のモデルの一方的な押し付けが、世界貿易を後退させるかもしれない。もし、そうであるなら、地政学的な緊張が生まれてもおかしくない。アメリカとその同盟国はそうなることを望んではいないが、もし、中国が不況に悩んで国内に不満が充満すれば、繁栄していたころに比べてずっと好戦的になるかもしれない」
同誌は最後に、なぜ中国は変わらないのかを考察している。「ひとつの理由は、習近平が人の話を聞こうとしないからだ」。中国が開放経済に移行してから30年間の成功は、海外に対して開放を進め経済改革を進めたからだが、習近平が支配するようになってからは、経済の専門家は脇に押しやられてしまった」。そしてもうひとつあるという。「それは習近平が、たとえ代償を払うことになるとしても、国家の安全保障を経済的繁栄よりも優先するようになったからだ」。
 ジ・エコノミストが指摘していることは以上のようなことだが、ざっと読んで完全な自由貿易体制と習近平体制との比較で述べている点は、やや単純化が過ぎるような気がする。習近平ほどの経済に暗い独裁者でなくとも、大国は民主主義を標榜しながら保護主義を展開することは珍しくない。TPPなどでさんざん日本に妥協を強いたアメリカは、いまやバイデンのもとで保護主義に傾斜している。
ジ・エコノミストが指摘していることは以上のようなことだが、ざっと読んで完全な自由貿易体制と習近平体制との比較で述べている点は、やや単純化が過ぎるような気がする。習近平ほどの経済に暗い独裁者でなくとも、大国は民主主義を標榜しながら保護主義を展開することは珍しくない。TPPなどでさんざん日本に妥協を強いたアメリカは、いまやバイデンのもとで保護主義に傾斜している。
アメリカの保護主義については、ジ・エコノミストは日本製鉄のUSスティール買収をバイデンが阻止しようとしていることや、対中国通商政策での保護主義について論じてはいる。それでも自由貿易が理想とされるのは、同誌が19世紀の自由貿易運動の牙城だったことと関係があるだろう。たしかにいまの中国の経済政策は、非現実的なために失敗するだろう。しかし、ある程度の成功を求めるには、お互いに自由貿易と保護主義との間に妥協点を見出すしかない。習近平の中国はそれすらできなくなっているということだろう。
●こちらもご覧ください
中国経済は回復できるのか(1)習近平の「新質生産力」はなぜダメな政策なのか
中国経済は回復できるのか(2)巨額の国債を発行しても蟻地獄からは出られない
インド経済は世界をリードするのか(1)モディ首相が率いる最速経済をグラフで見る
上海で警察隊とデモ隊が衝突!;ウルムチとゼロコロナを批判、習近平退陣の連呼も【増補】
中国の不動産バブル崩壊!(1)恒大集団が社債利払いに失敗した
中国の不動産バブル崩壊!(2)レッドラインを超えて感染する危機
中国の不動産バブル崩壊!(3)住宅にも波及し始めた価格下落
中国の不動産バブル崩壊!(4)全人代はついに不動産税を課す決定をした
中国の不動産バブル崩壊!(5)恒大集団がデフォルトした裏事情をみる
中国の不動産バブル崩壊!(6)残された解決策は政府による救済のみに
中国の不動産バブル崩壊!(7)連鎖的な金融機関の破綻がとまらない
中国の不動産バブル崩壊!(8)政府の救済策36項目は本当に効くのか?
中国の不動産バブル崩壊!(9)「習近平やめろ!」はゼロコロナとバブル崩壊への怒りの爆発だった
中国の不動産バブル崩壊(10)医療腐敗撲滅キャンペーンは不況から目をそらすためか
中国の不動産バブル崩壊!(11)習近平の経済体制が深刻な危機状態へ
中国の不動産バブル崩壊!(12)債務デフォルトは個人レベルにまでおよんでいる
ポスト・コロナ経済の真実(1)イーロン・マスクのツイッター買収が示唆する近未来
ポスト・コロナ経済の真実(2)中国は脱ゼロコロナで経済を回せるか
ポスト・コロナ経済の真実(3)中国のいまの「経済復活」は本物なのか
ポスト・コロナ経済の真実(4)植田日銀総裁の金融政策を予想する
ポスト・コロナ経済の真実(5)なぜ中国経済にリバウンドが起こらないのか
ポスト・コロナ経済の真実(6)中国GDP4.5%上昇に潜む落とし穴
ポスト・コロナ経済の真実(7)パンデミックは政治家たちの試金石でもあった
ポスト・コロナ経済の真実(8)中国の経済回復が失速したのは「信頼」を失ったから
ポスト・コロナ経済の真実(9)信頼崩壊の中国経済をグラフで読み取る
ポスト・コロナ経済の真実(10)目で見る今の中国経済の「惨状」
ポスト・コロナ経済の真実(11)テレワークは生産性を高めるという幻想の終わり
ポスト・コロナ経済の真実(12)中国はデフレに向かって急速に萎縮中だ!
ポスト・コロナ経済の真実(13)中国が米国に追いつくのはずっと先というのは本当?
ポスト・コロナ経済の真実(14)経済低迷の中で中国製EVが躍進する謎
ポスト・コロナ経済の真実(15)中国政府はバブル崩壊の悲惨なデータを隠し始めた
ポスト・コロナ経済の真実(16)中国のデフレは波及しないというのは本当か?
ポスト・コロナ経済の真実(17)米国経済が本格的に回復しないのは心理的問題なのか?
ポスト・コロナ経済の真実(18)中国バブル崩壊は政府が融資したくらいでは終わらない


