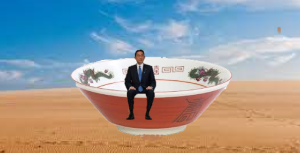ウクライナ戦争と経済(30)戦争してもロシア経済は大丈夫という説を再検討する
いまもロシアは西側による経済制裁をものともせず、ウクライナとの戦争を続けている。少なくとも各種の経済データを見れば、しばらくは持続できるように見える。しかし、統計という数値の背後にある、個々の現実をみたとき、同じ結論を引き出せるだろうか。ここではロシアという巨大な空間における、加工の度合いの低い、その意味で生にちかい事象をみてみよう。
 外交誌フォーリンアフェアーズ電子版9月2日付にタフツ大学准教授クリス・ミラーが「ロシア経済は崖っぷちにあるのか? ウクライナ戦争を継続するモスクワの苦闘」を寄稿している。ミラーについては後に詳しく紹介することとして、経済的観点からロシア現代史を研究してきた研究者である。その少壮ロシア研究者が、このところ多くの論者が指摘するようになった、戦時におけるロシア経済の強靭さについて、少し異なった視点から論じている。
外交誌フォーリンアフェアーズ電子版9月2日付にタフツ大学准教授クリス・ミラーが「ロシア経済は崖っぷちにあるのか? ウクライナ戦争を継続するモスクワの苦闘」を寄稿している。ミラーについては後に詳しく紹介することとして、経済的観点からロシア現代史を研究してきた研究者である。その少壮ロシア研究者が、このところ多くの論者が指摘するようになった、戦時におけるロシア経済の強靭さについて、少し異なった視点から論じている。
もちろん、ミラーもウクライナ侵攻後のロシア経済が、欧米を中心とする世界から経済制裁を受けつつも、一定の安定を実現していることは認める。そして、それがロシアの経済政策のテクノクラティック(経済官僚的)な優秀さと、石油と天然ガスによる収入が途絶えていないことから生じているとする点では、これまで紹介してきた欧米のジャーナリズムと同じ認識に立っているといえる。
 異なっているのは、マクロ経済的な経済データを尊重しつつも、そこに現れてくる数値だけではなく、いや、それ以上に背後で生じているばらばらの事実に注目する点である。「ロシア経済はなおも傷ついているといってよい。2008年の金融危機のときより減速しているし、危機からの回復が生じているわけでもない」「時間がたつにつれて、戦争のコストとロシアの他の分野への制裁による影響は大きくなっていくだろう」。(グラフはwsj.comより;ロシア国債が「復活」したというグラフである)
異なっているのは、マクロ経済的な経済データを尊重しつつも、そこに現れてくる数値だけではなく、いや、それ以上に背後で生じているばらばらの事実に注目する点である。「ロシア経済はなおも傷ついているといってよい。2008年の金融危機のときより減速しているし、危機からの回復が生じているわけでもない」「時間がたつにつれて、戦争のコストとロシアの他の分野への制裁による影響は大きくなっていくだろう」。(グラフはwsj.comより;ロシア国債が「復活」したというグラフである)
ミラーがまず指摘するのは、いま手に入るロシアの経済データには疑いをもったほうがいいということだ。ロシアの産業全体での生産低下は2%ですんでいるというが、これは石油と天然ガスの生産を含んだ数値であり、たとえば製造業だけを見れば4.5%もの落ち込みがある。また、インフレーションは18%から15%まで低下したとされているが、賃金が昨年との比較で6%もの下落をしていることを考慮すべきだろう(賃金が下がれば購買意欲が低下するからインフレは抑えられる)。しかも、こうした数値にはかなりの操作が加わっているとの指摘もあるという。
インフレの数値については、もっと問題がある。たとえば、iPhoneなどに見られるようにいまやロシアで買うことが困難になっている製品は多い。自動車のレクサスなどにいたっては、そもそも買えないのである。つまり、買いたいものが自由に買えない状態のとき、統計学的に整理された数値としてあがってきたインフレ率は、そのまま経済の現実を反映していないというわけだ。
さらにインフレにこだわれば、製品のクオリティが下がっているのに、本来ならば同じものとして計算はできない。これも例をあげれば、ロシア産の自動車にはエアーバッグやアンチロック・ブレーカーが取り付けられなくなっている。実際には安くなって当然のものだろう。また、下落しているのは賃金だけでなく、政府によって年金も減額されており、そのため平均収入が低下して、購買力が落ちていることも、インフレ率を計測するさいに、歪みを生み出す可能性が大きいという。
 ミラーは石油と天然ガスについても、EUによる制裁は今年12月にならないと本格化することはなく、また間接的な売買をへて中国やインドに流れていることを一通り述べているが、大筋の話としてはこれまで報道されていることとそれほど異ならない。ただし、ロシアの石油は国際価格標準からは20ドルほど安く売らざるを得なくなっており、モスクワ政府に入る石油税収はせいぜい今年1月と同レベルであり、天然ガスにいたってはEUへの供給を減らしてからは、政府に入るガス税収も落ちているという指摘がある。(グラフはwsj.comより:ロシアの通貨ルーブルが侵攻以前より為替市場で高くなったことが示されている)。
ミラーは石油と天然ガスについても、EUによる制裁は今年12月にならないと本格化することはなく、また間接的な売買をへて中国やインドに流れていることを一通り述べているが、大筋の話としてはこれまで報道されていることとそれほど異ならない。ただし、ロシアの石油は国際価格標準からは20ドルほど安く売らざるを得なくなっており、モスクワ政府に入る石油税収はせいぜい今年1月と同レベルであり、天然ガスにいたってはEUへの供給を減らしてからは、政府に入るガス税収も落ちているという指摘がある。(グラフはwsj.comより:ロシアの通貨ルーブルが侵攻以前より為替市場で高くなったことが示されている)。
すでに指摘したエネルギー産業以外の分野については、たとえば、乗用車、トラック、鉄道車両、光ファイバーの生産は1年前と比べて半分に減少した。テキスタイル(布地)や食料加工の分野などでは、なんとか横這いか多少の上昇を見せているところもあるといった状況だ。製造業で制裁によるマイナスの影響が大きくなった原因は、やはり、日本、アメリカ、ヨーロッパなどからの進出企業が引き揚げたことだろう。撤退後に同じような製品をロシア企業でもつくれるようにした分野もあるが、クオリティ(質)の低下は防ぎようがないとのことだ。
「いっぽうで、ロシア政府はウクライナ侵攻後の半年で代わりになるような事業を起こし、サプライチェーンの再建に乗り出して、経済制裁の対象となっていない輸入品を売ってくれる国を見出してきた。他方では、ロシア企業はそれまでの在庫を使って製造活動を続けてきたものの、いまや必要な部品を手にいれるのに苦労している。そこまでやっても月例データを見れば、工業製品や部品の輸入が、ウクライナ侵攻前のレベルからはるかに減少したことが分かる」
深刻な問題を抱えているのは、ウクライナやシベリアに散在する「モノゴロドス」と呼ばれる単一工場あるいは単一産業で成立している都市で、こうした都市では製造のストップが住民の収入を断つことなる。モノゴロドスでは、レイオフが抗議行動や社会反乱を引き起こしてきた歴史があり、シンクタンクの調査では、現在のモノゴロドスの半分は、経済政策のために直接的で急激な衝撃を受けていることが分かっている。しかし、それに対してロシア政府がどこまで援助できるのか、いまのところ不明なままだという。
 このように国内に多くの問題を抱えるなかで、アメリカ産のロケット砲などを用いるウクライナの反撃が本格化している。すでに4月でロシア政府は政府支出の数値公表を停止したが、最後の4月の数値でも防衛費の支出が例年にくらべて40%も上昇していた。「戦争の費用は中央政府のバランスシートを著しく悪化させるだけでなく、ウクライナに『義勇軍』を派遣することを要求されている、地方政府のバランスシートも破壊してしまうことになる」
このように国内に多くの問題を抱えるなかで、アメリカ産のロケット砲などを用いるウクライナの反撃が本格化している。すでに4月でロシア政府は政府支出の数値公表を停止したが、最後の4月の数値でも防衛費の支出が例年にくらべて40%も上昇していた。「戦争の費用は中央政府のバランスシートを著しく悪化させるだけでなく、ウクライナに『義勇軍』を派遣することを要求されている、地方政府のバランスシートも破壊してしまうことになる」
ミラーが指摘したいのは、たしかに発表されたデータや推計によるマクロ的な数値は、ロシア経済がいましばらくは戦争を遂行し、国民の生活もなんとか安定したまま維持できるかのように見えるが、現実にロシア国内で起こっていることをひとつひとつ見て行けば、とても長期に維持できるような状態ではないということである。
「ロシア経済は確かにクレムリン政府が戦争を続けていても、目の前で崩壊しつつあるわけではない。しかしながら、ロシアという国家は、急激な景気後退、低い生活水準のさらなる低下、そして、景気回復がすぐにはやってこない現実に対する国民の失望に直面している」
 こうした論文を書いたクリス・ミラーはこれまでもソ連時代の経済崩壊が、なぜ80年代に起こったかを歴史的に解明する著作『ソ連経済を救う戦い』(先日物故したゴルバチョフに多くの責任があるとしている)などを書いており、今年の2月24日のロシアによるウクライナ侵攻のさいには、翌日、ニューヨーク・タイムズ紙に「なぜプーチンは再び戦争するのか? 彼は勝利を確信しているから」というオピニオンを寄せている。ただし、このオピニオンでは、ロシア軍はウクライナ軍を圧倒することになっており、この点で必ずしもプーチンの錯誤とウクライナ軍の戦争準備について、気づいていたとはいえないかもしれない。
こうした論文を書いたクリス・ミラーはこれまでもソ連時代の経済崩壊が、なぜ80年代に起こったかを歴史的に解明する著作『ソ連経済を救う戦い』(先日物故したゴルバチョフに多くの責任があるとしている)などを書いており、今年の2月24日のロシアによるウクライナ侵攻のさいには、翌日、ニューヨーク・タイムズ紙に「なぜプーチンは再び戦争するのか? 彼は勝利を確信しているから」というオピニオンを寄せている。ただし、このオピニオンでは、ロシア軍はウクライナ軍を圧倒することになっており、この点で必ずしもプーチンの錯誤とウクライナ軍の戦争準備について、気づいていたとはいえないかもしれない。
もうひとつ注意すべきなのは、今回紹介した論文は『フォーリンアフェアーズ』に寄稿した論文であることだ。ウクライナ侵攻後の同誌は、元ネオコンのフランシス・フクヤマが自由と民主の復活をこの戦争に見る旨の論文を載せたり(ほとんどネオコンに復帰したといってよい)、いわゆるリベラル・ホーク(リベラルなタカ派)のロバート・ケイガンによるウクライナ戦争を「自由と民主を維持する代償」であると論じる論文が載ったりと、あたかもイラク戦争時のネオコン+リベラル・ホーク路線(2つは実は別のものだが)の論調になっていることは断っておきたい。
 したがって、ミラーの寄稿も勘ぐれば、最近多くなった「ロシアに対する経済制裁は効いていない」という指摘に対して、リベラル・ホーキッシュな立場から反論するという任務を負っているのかもしれない。とはいえ、経済雑誌などは切れ味がよいように見えて、実は、アグリゲート(総和)した数値で分析したものでしかない。そうした「加工品」では見えない、生により近いロシアの現状が、部分的にせよ描かれていることも確かである。
したがって、ミラーの寄稿も勘ぐれば、最近多くなった「ロシアに対する経済制裁は効いていない」という指摘に対して、リベラル・ホーキッシュな立場から反論するという任務を負っているのかもしれない。とはいえ、経済雑誌などは切れ味がよいように見えて、実は、アグリゲート(総和)した数値で分析したものでしかない。そうした「加工品」では見えない、生により近いロシアの現状が、部分的にせよ描かれていることも確かである。
経済データでは文句なしに好調に見えたのに、あっという間に崩壊してバブルだったことが分かるということが起こる。なんとか維持できそうだと思われた経済が、もろくも崩壊して愕然とする前に、冷静に再検討しておくことは無駄ではない。この論文が最近の欧米ジャーナリズムと違う根本的な部分は「ロシア経済はどれくらい長くもつか」つまり時間の問題だと思う。私は「いつまでなら維持できる」とか「これこれの条件が失われれたら危機的状態になる」といった、時間的な条件を含めた議論をもう始めるべきだと思う。これは「統計」という危うい認識法で見ているさいのリスク回避行動である。
●こちらもご覧ください
ロシア経済制裁の失敗が示す未来;軍事の意味が改めて問われるとき
経済制裁下のロシア国民の消費生活;見かけよりずっと健全な理由は何か
ウクライナ戦争が引き起こした世界的食糧高騰;途上国の貧困層を激しく直撃している
ウクライナ戦争と経済(1)米国FRBは戦争でも金利を上げるのか
ウクライナ戦争と経済(2)アメリカと西側の金融制裁は効いているのか?
ウクライナ戦争と経済(3)ロシアの侵略で中国の金融が欠陥を暴露された
ウクライナ戦争と経済(4)ロシア通貨ルーブルの「強靭さ」は本物か
ウクライナ戦争と経済(5)ロシアの石油を売買する「抜け穴」を覗く
ウクライナ戦争と経済(6)穀物市場の高騰と忍び寄る保護主義の恐怖
ウクライナ戦争と経済(7)ウクライナの復興にはいくらかかるか
ウクライナ戦争と経済(8)米国の8.5%のインフレはプーチンのせいなのか
ウクライナ戦争と経済(9)この戦争の影響をしっかりとグラフで見つめる
ウクライナ戦争と経済(10)米株式市場は戦争で根本的に変わった
ウクライナ戦争と経済(11)日本の通貨YENは没落の危機を迎える
ウクライナ戦争と経済(12)ロシアの街角で若者たちがコーヒーを楽しめる謎
ウクライナ戦争と経済(13)ハイテク株とビットコインが一緒に暴落する必然
ウクライナ戦争と経済(14)企業物価上昇10%で日本も高インフレか
ウクライナ戦争と経済(15)米国のダウが1164ドル超の暴落で不安が広がる
ウクライナ戦争と経済(16)日本はインフレからスタグフレーションに向かう
ウクライナ戦争と経済(17)米国がスタグフレーションになるこれだけの根拠
ウクライナ戦争と経済(18)すでにスタグフレーション下でのビジネスが論じられている
ウクライナ戦争と経済(19)米国インフレ8.6%に対してクルーグマンはどう考えるか
ウクライナ戦争と経済(20)円安で海外投資家に買い叩かれる日本
ウクライナ戦争と経済(21)日本だけが低インフレなのではない?
ウクライナ戦争と経済(22)ホーキッシュな政治と経済が危機を拡大する
ウクライナ戦争と経済(23)米経済は「自己実現的予言」でリセッションを引き起こす
ウクライナ戦争と経済(24)米国のインフレをしっかり目で見ておこう
ウクライナ戦争と経済(25)米国の住宅賃貸料の急騰が意味するもの
ウクライナ戦争と経済(26)米国はついに「スタグフレーション」に突入した!
ウクライナ戦争と経済(27)インフレは敵なのか味方なのか
ウクライナ戦争と経済(28)いま穀類の価格が下落している理由は何か?
ウクライナ戦争と経済(29)ロシア経済はなぜ経済制裁を受けても破綻しないのか?
ウクライナ戦争と経済(30)戦争をしてもロシア経済は大丈夫だという説を再検討する
ウクライナ戦争と経済(31)ついに日本を食料危機が襲う?
ウクライナ、台湾、そして日本(6)そのとき習近平はなにをしていたのか