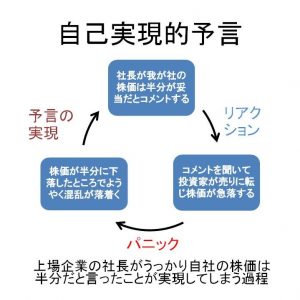生きていると否応なく生じる隙間;『街の上で』若葉竜也の「素朴」さに注目!
『街の上で』(2019・今泉力哉監督)
映画評論家・内海陽子
 東京というところを一言で説明するのは難しい。わたしは台東区生まれで、北区、足立区と移り住んだが、住んだ記憶のない浅草に行くと、胸の奥がじゅっとするように懐かしい。幼いころ、よく遊びに連れて行かれたデパートがあり、のちにそこに務めたこともあるからだ。ところが四国出身の知人が、浅草に住んだら嫌な目にあってこりごりしたと言う。人と人の縁があるから、運が悪かったのだろうと思うが、彼の中でその思いが凝り固まっているのが気になった。知人は西の杉並区に転居して落ち着いたようだが、きっと東京の東側と西側では人情もしきたりも違うのだろう。遠く離れた村と村が違うように。
東京というところを一言で説明するのは難しい。わたしは台東区生まれで、北区、足立区と移り住んだが、住んだ記憶のない浅草に行くと、胸の奥がじゅっとするように懐かしい。幼いころ、よく遊びに連れて行かれたデパートがあり、のちにそこに務めたこともあるからだ。ところが四国出身の知人が、浅草に住んだら嫌な目にあってこりごりしたと言う。人と人の縁があるから、運が悪かったのだろうと思うが、彼の中でその思いが凝り固まっているのが気になった。知人は西の杉並区に転居して落ち着いたようだが、きっと東京の東側と西側では人情もしきたりも違うのだろう。遠く離れた村と村が違うように。
 わたしはいわば東京の東北出身なので、西側へ行くと感触が違うと思うことがある。演劇を観に西側の小さな劇場へ行ったとき、若い男性に略図を見せて道を尋ねたら、じっくり考え親切に的確に教えてくれた。平凡な眼鏡の奥の目が知的にきらめいて、思わず「お名前をお聞かせください」と言いたくなるほどだった。いい人に会えて運がよかったのだろうが、土地の文化度も高いのだろうと納得した。この映画の舞台である「下北沢」は南西側にあるが、この地もよそ者に向けて心が開かれているという印象がある。
わたしはいわば東京の東北出身なので、西側へ行くと感触が違うと思うことがある。演劇を観に西側の小さな劇場へ行ったとき、若い男性に略図を見せて道を尋ねたら、じっくり考え親切に的確に教えてくれた。平凡な眼鏡の奥の目が知的にきらめいて、思わず「お名前をお聞かせください」と言いたくなるほどだった。いい人に会えて運がよかったのだろうが、土地の文化度も高いのだろうと納得した。この映画の舞台である「下北沢」は南西側にあるが、この地もよそ者に向けて心が開かれているという印象がある。
 ただし、この映画の主人公・荒川青(若葉竜也)はあまり気の利いた青年ではない。恋人の雪(穂志もえか)に別れ話を切り出されて動揺を隠せず、別れることを拒否する。その態度があまりに惨めに見えるので、彼のこれからの人生はきびしいだろうなとため息がもれる。務める古着屋に客は少なく、彼はやむなく読書する日々だが、そこに目を留めた女性映画監督から出演要請の声がかかる。どうしたものかと迷っていると、飲み屋の知り合いが「それは告白だ」と断言する。雪に未練たっぷりなのに、ほかの女性からの誘いがあれば話は別、とばかりに彼はにわかに自主制作映画出演に前向きになる。
ただし、この映画の主人公・荒川青(若葉竜也)はあまり気の利いた青年ではない。恋人の雪(穂志もえか)に別れ話を切り出されて動揺を隠せず、別れることを拒否する。その態度があまりに惨めに見えるので、彼のこれからの人生はきびしいだろうなとため息がもれる。務める古着屋に客は少なく、彼はやむなく読書する日々だが、そこに目を留めた女性映画監督から出演要請の声がかかる。どうしたものかと迷っていると、飲み屋の知り合いが「それは告白だ」と断言する。雪に未練たっぷりなのに、ほかの女性からの誘いがあれば話は別、とばかりに彼はにわかに自主制作映画出演に前向きになる。
監督の高橋(萩原みのり)は青の屈託ありげな表情に惚れこんだのだろうが、いざ撮影ともなれば自意識でガチガチになった青は何度やってもうまくいかない。自然な演技というものがいかにプロフェッショナルなものであるかがよくわかる。そしてここでガチガチになる若葉竜也は、その裏返しを見せるプロフェッショナルであるということもわかる。『愛がなんだ』(2019・今泉力哉監督)で「幸せになりたいっすね」と吐露して善男善女のハートをつかんだ彼は、この映画で(この街で)はたして幸せをつかめるだろうか。
 飲み会の席に呼ばれても身の置き所がない青に、屈託なく近づくのが衣裳担当スタッフのイハ(中田青渚)で、どういう風の吹き回しか、彼女は青を自宅マンションに誘う。といってもお茶を飲みながら失恋話をするだけなのだが、このあたりから今泉力哉一流の、男と女の“心ころがし”の腕が冴えわたる。当然ながら青は彼女の魂胆がわからず、かすかな希望と欲望を捨てきれず、あげくが泊まることになってしまう。このオチは言えない。
飲み会の席に呼ばれても身の置き所がない青に、屈託なく近づくのが衣裳担当スタッフのイハ(中田青渚)で、どういう風の吹き回しか、彼女は青を自宅マンションに誘う。といってもお茶を飲みながら失恋話をするだけなのだが、このあたりから今泉力哉一流の、男と女の“心ころがし”の腕が冴えわたる。当然ながら青は彼女の魂胆がわからず、かすかな希望と欲望を捨てきれず、あげくが泊まることになってしまう。このオチは言えない。
 すでに三人の女性が青の前に登場したが、四人目もいる。登場は少し前だが、古本屋の店員・田辺(古川琴音)で、亡き店主の愛人だったと噂のある雰囲気美人だ。ちょっとした行き違いで青との間に不穏な空気が流れたことが良い結果になり、青の撮影の予行演習を手伝うことになる。後日、映画の上映会で青の登場シーンがないことが腑に落ちず、監督の高橋に詰め寄るシーンは、この映画のハイライトのひとつだ。返答に窮した高橋がイハに助けを求め、イハが話を終わらせる。これは女心に焦点を当てた“心ころがし”だろうか。
すでに三人の女性が青の前に登場したが、四人目もいる。登場は少し前だが、古本屋の店員・田辺(古川琴音)で、亡き店主の愛人だったと噂のある雰囲気美人だ。ちょっとした行き違いで青との間に不穏な空気が流れたことが良い結果になり、青の撮影の予行演習を手伝うことになる。後日、映画の上映会で青の登場シーンがないことが腑に落ちず、監督の高橋に詰め寄るシーンは、この映画のハイライトのひとつだ。返答に窮した高橋がイハに助けを求め、イハが話を終わらせる。これは女心に焦点を当てた“心ころがし”だろうか。
 忘れてはならない、友情出演の成田凌がいる。NHKの連ドラ出演のキャリアもある人気俳優が自主映画に出演するという格好いい役どころで、気圧されている青に「映画に大きいも小さいもありませんから」とさらっと言う。もちろん、読書する姿の撮影は余裕綽々でこなし、青はまぶしいものを観たような気持で見送る。この、素人さんの素朴な崇拝のまなざし、というのを若葉竜也はまことに感じよく演じる。両者が役割を交代してみたら、と考えると違いは明らかだ。もはや成田凌にはこの素朴な演技はできないだろう。いや、できないというより、周囲の目がもはやそれを受け付けなくなっている、と言ったほうがいいだろう。それでは成田凌の見せ場はどこにあるのかといえば終盤のワンシーンにある。思わず膝を打つが、当然ながらここでは言えない。
忘れてはならない、友情出演の成田凌がいる。NHKの連ドラ出演のキャリアもある人気俳優が自主映画に出演するという格好いい役どころで、気圧されている青に「映画に大きいも小さいもありませんから」とさらっと言う。もちろん、読書する姿の撮影は余裕綽々でこなし、青はまぶしいものを観たような気持で見送る。この、素人さんの素朴な崇拝のまなざし、というのを若葉竜也はまことに感じよく演じる。両者が役割を交代してみたら、と考えると違いは明らかだ。もはや成田凌にはこの素朴な演技はできないだろう。いや、できないというより、周囲の目がもはやそれを受け付けなくなっている、と言ったほうがいいだろう。それでは成田凌の見せ場はどこにあるのかといえば終盤のワンシーンにある。思わず膝を打つが、当然ながらここでは言えない。
 この映画の魅力は、人と人との視線の交わしぐあい、ふるまいのずれ、早とちりを丁寧に愛でているところにある。つまり生きていると否応なく生じる人と人の隙間のようなところを、悲しみ笑いながら、深いところで応援している。たとえ大きな事件が起こらなくても、人は生きているだけでいくつもの事件を乗り切っているのだということがよくわかる。「下北沢」という街がそういう人々を大事に乗せて動いているという風に感じられる。この街が宙に飛ばされても大丈夫かもしれない。
この映画の魅力は、人と人との視線の交わしぐあい、ふるまいのずれ、早とちりを丁寧に愛でているところにある。つまり生きていると否応なく生じる人と人の隙間のようなところを、悲しみ笑いながら、深いところで応援している。たとえ大きな事件が起こらなくても、人は生きているだけでいくつもの事件を乗り切っているのだということがよくわかる。「下北沢」という街がそういう人々を大事に乗せて動いているという風に感じられる。この街が宙に飛ばされても大丈夫かもしれない。
◎2021年4月9日より順次公開
内海陽子プロフィール
 1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
『愛がなんだ』:悲しみとおかしみを包み込む上質なコートのような仕上がり
『バースデー・ワンダーランド』:情感とスピード感に満ちた贅沢なひととき
『家族にサルーテ! イスキア島は大騒動』:けっして自分の生き方を諦めない大人たちを描きぬく
『エリカ38』:浅田美代子が醸し出す途方に暮れた少女のおもかげ
『ファイティング・ダディ 怒りの除雪車』:本作が断然お薦め! 頑固一徹闘うジジイ
『DANCE WITH ME ダンス ウィズ ミー』:正常モードから異常モードへの転換センスのよさ
『記憶にございません!』:笑いのお座敷列車 中井貴一の演技が素敵!
RBGがまだ世間知らずだったとき:ルース・B・ギンズバーグの闘い
『劇場版おっさんずラブ LOVE or DEAD』常に新鮮で的確な田中圭のリアクション
千葉雄大の孤軍奮闘にハラハラ;『スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼』
成田凌から飛び出す得体のしれないもの;ヨコハマ映画祭・助演男優賞受賞に寄せて