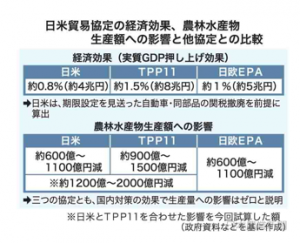カトリーヌ・ドヌーヴの物語を生む力
『真実』(2019・是枝裕和監督)
映画評論家・内海陽子
 ミュージカル『シェルブールの雨傘』(1964・ジャック・ドゥミ監督)に代表されるように、若き日のカトリーヌ・ドヌーヴは陶器の人形のようだったが、年配になるにつれ独特の愛嬌がにじむようになった。身体がどんなにふくよかになっても、脚の美しさはそのままなのが驚異的で、それを確認するたびに畏敬の念と安堵感を覚える。幾人もの監督が作るドラマティックな世界で、さまざまな女のイメージを提示してきた彼女が、『真実』では自分自身をさらすことにあっさり同意したようである。それが明るい親近感を生む。異国の監督である是枝裕和は、いったいどういうアプローチをしたのだろう。
ミュージカル『シェルブールの雨傘』(1964・ジャック・ドゥミ監督)に代表されるように、若き日のカトリーヌ・ドヌーヴは陶器の人形のようだったが、年配になるにつれ独特の愛嬌がにじむようになった。身体がどんなにふくよかになっても、脚の美しさはそのままなのが驚異的で、それを確認するたびに畏敬の念と安堵感を覚える。幾人もの監督が作るドラマティックな世界で、さまざまな女のイメージを提示してきた彼女が、『真実』では自分自身をさらすことにあっさり同意したようである。それが明るい親近感を生む。異国の監督である是枝裕和は、いったいどういうアプローチをしたのだろう。
 『真実』というタイトルの自伝を発表したフランスの大女優ファビエンヌ(カトリーヌ・ドヌーヴ)のもとに、アメリカで暮らす脚本家の娘・リュミール(ジュリエット・ビノシュ)と夫のハンク(イーサン・ホーク)と娘がお祝いにやって来る。事前に読ませてもらえなかったリュミールが目を通してみれば、自伝は真実とはほど遠いもので、ファビエンヌの親友でライバルであった女優サラについても触れられていない。子供のころ「サラおばさん」と呼んで慕ったリュミールは不満を隠さないが、問いただしても母は涼しい顔だ。
『真実』というタイトルの自伝を発表したフランスの大女優ファビエンヌ(カトリーヌ・ドヌーヴ)のもとに、アメリカで暮らす脚本家の娘・リュミール(ジュリエット・ビノシュ)と夫のハンク(イーサン・ホーク)と娘がお祝いにやって来る。事前に読ませてもらえなかったリュミールが目を通してみれば、自伝は真実とはほど遠いもので、ファビエンヌの親友でライバルであった女優サラについても触れられていない。子供のころ「サラおばさん」と呼んで慕ったリュミールは不満を隠さないが、問いただしても母は涼しい顔だ。
 ファビエンヌは家庭を大事にすることよりも女優として映像の中で生きることを選んだのだからなんの後悔もない、という建前をくずさないが、はたしてそれは言葉通りだろうか。彼女が出演を承諾し、現在撮影中のSF映画は、難病治療のため宇宙へ行って年を取らなくなった母と、地球で年を重ねていく娘の物語で、ファビエンヌは娘役だ。母を演じるのはサラの再来ともてはやされているマノン(マノン・クラヴェル)で、ファビエンヌは闘志をむき出しにする。折悪しく、長年、ファビエンヌに仕えた秘書が辞職し、代わりにリュミールが撮影につき添うことになり、母娘の愛憎関係はねじれた二重構造になる。
ファビエンヌは家庭を大事にすることよりも女優として映像の中で生きることを選んだのだからなんの後悔もない、という建前をくずさないが、はたしてそれは言葉通りだろうか。彼女が出演を承諾し、現在撮影中のSF映画は、難病治療のため宇宙へ行って年を取らなくなった母と、地球で年を重ねていく娘の物語で、ファビエンヌは娘役だ。母を演じるのはサラの再来ともてはやされているマノン(マノン・クラヴェル)で、ファビエンヌは闘志をむき出しにする。折悪しく、長年、ファビエンヌに仕えた秘書が辞職し、代わりにリュミールが撮影につき添うことになり、母娘の愛憎関係はねじれた二重構造になる。
 このSF映画が三流くさいのは設定だけでも明らかだ。ファビエンヌは、名女優たるもの手抜きは許されない、とばかりに情感のこもった念入りな演技をするが、監督に「もっとさらっとお願いします」というようなことを言われてくさる。アドリブでわざと転んでひざを傷めもする。母はなかなか可愛らしいのである。リュミールは、女優の母を撮影現場で見守ることに面白みを感じ始め、脚本家としての意欲が増してきたようだ。その証拠に、辞職した秘書リュック(アラン・リボル)を呼び戻すための「ひと芝居」を母のために書き、わずかながら母と娘は距離を縮めるのである。
このSF映画が三流くさいのは設定だけでも明らかだ。ファビエンヌは、名女優たるもの手抜きは許されない、とばかりに情感のこもった念入りな演技をするが、監督に「もっとさらっとお願いします」というようなことを言われてくさる。アドリブでわざと転んでひざを傷めもする。母はなかなか可愛らしいのである。リュミールは、女優の母を撮影現場で見守ることに面白みを感じ始め、脚本家としての意欲が増してきたようだ。その証拠に、辞職した秘書リュック(アラン・リボル)を呼び戻すための「ひと芝居」を母のために書き、わずかながら母と娘は距離を縮めるのである。
ところで、この映画は字幕版と吹き替え版があり、わたしは吹き替え版で見たが、声優に選ばれたのは宮本信子だ。彼女なら常とは違う声も出せるはずだが、発声は従来の宮本信子のままである。自我の強いフランス人女優を、細やかな表現を得意とする宮本信子が演じる。彼女によるファビエンヌの再演、もしくは批評がなされていると言ってもいいだろう。ファビエンヌの激しい言葉や痛烈な皮肉にも、やわらかな色気が添えられ、知的な印象になる。隠された母性がふんわり画面をおおっているような感じになる。
 このように思うのは私の勝手で、それはカトリーヌ・ドヌーヴという女優が観客の妄想を喚起する特別な存在であり、さらなる物語を生む力を持っているからである。ただの実力派女優というレベルではなく、どんなに自分自身をさらしているように見えても、実のところリアルな日常を見せているわけではない。ファビエンヌの現在の夫は料理が得意で「あなたのティラミスには飽きたわ」などと彼女に言われるが、ファビエンヌは料理ができないのではなく、料理をしないのである。それが高慢な印象を与えないどころか、そういうことは彼女の役割ではない、と誰をも納得させるところがいい。
このように思うのは私の勝手で、それはカトリーヌ・ドヌーヴという女優が観客の妄想を喚起する特別な存在であり、さらなる物語を生む力を持っているからである。ただの実力派女優というレベルではなく、どんなに自分自身をさらしているように見えても、実のところリアルな日常を見せているわけではない。ファビエンヌの現在の夫は料理が得意で「あなたのティラミスには飽きたわ」などと彼女に言われるが、ファビエンヌは料理ができないのではなく、料理をしないのである。それが高慢な印象を与えないどころか、そういうことは彼女の役割ではない、と誰をも納得させるところがいい。
 彼女がゴージャスな豹柄のコートをはおって愛犬の散歩に出るシーンがあるが、愛犬があまり彼女を慕っていないように見えるのがいかにもおかしい。女優として観客には最高のマジックを仕掛けることができても、犬にはどうも通用しないようだ。監督・脚本はもとより、編集も手がける是枝裕和は、何を考えたか、エンディングでこの散歩シーンを長めに流してみせる。その映像は、まるで八ミリカメラで撮ったような親愛感にあふれているが、孤独と向き合って生きて行く大女優の寂しさと華やぎをも同時に伝えてくる。ハサミ(編集権)を持っている者の勝ち、という言葉がふと頭に浮かぶ。
彼女がゴージャスな豹柄のコートをはおって愛犬の散歩に出るシーンがあるが、愛犬があまり彼女を慕っていないように見えるのがいかにもおかしい。女優として観客には最高のマジックを仕掛けることができても、犬にはどうも通用しないようだ。監督・脚本はもとより、編集も手がける是枝裕和は、何を考えたか、エンディングでこの散歩シーンを長めに流してみせる。その映像は、まるで八ミリカメラで撮ったような親愛感にあふれているが、孤独と向き合って生きて行く大女優の寂しさと華やぎをも同時に伝えてくる。ハサミ(編集権)を持っている者の勝ち、という言葉がふと頭に浮かぶ。
是枝裕和監督は、いままで、大女優を中心に据えてスケッチする、というような映画を作ってこなかったが、かなり向いているのではないかと思う。そこに求められるのは、細かな演技指導や映像テクニックではなく、ひたすら観察者に徹する辛抱強さではないだろうか。フランスという異国で、言葉がすぐには通じない環境であればなおさら、肝腎なのはひたすら対象を見つめ、見極めようとする意志である。その対象の持つ力が相乗効果をなし、生まれたのは、予想を超えるみごとな“女優論”であった。
内海陽子プロフィール
 1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
『愛がなんだ』:悲しみとおかしみを包み込む上質なコートのような仕上がり
『バースデー・ワンダーランド』:情感とスピード感に満ちた贅沢なひととき
『家族にサルーテ! イスキア島は大騒動』:けっして自分の生き方を諦めない大人たちを描きぬく
『エリカ38』:浅田美代子が醸し出す途方に暮れた少女のおもかげ
『ファイティング・ダディ 怒りの除雪車』:本作が断然お薦め! 頑固一徹闘うジジイ
『DANCE WITH ME ダンス ウィズ ミー』:正常モードから異常モードへの転換センスのよさ
『記憶にございません!』:笑いのお座敷列車 中井貴一の演技が素敵!