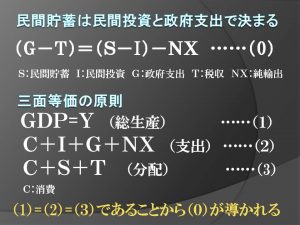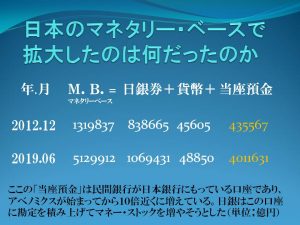正常モードから異常モードへの転換センスのよさ
『DANCE WITH ME ダンス ウィズ ミー』(2019・矢口史靖監督)
映画評論家・内海陽子
 ほぼ一貫して、特異な女子力を追求している矢口史靖監督の最新作はミュージカル映画。とはいっても、本作は“出演者が突然歌い出すミュージカルへの違和感”を発想の出発点にしているところが矢口流だ。老催眠術師(宝田明)によって、音楽が聴こえるとミュージカルスターになってしまう術をかけられた会社員、鈴木静香(三吉彩花)が、術を解いてもらうために催眠術師を追いかけるロードムービーである。
ほぼ一貫して、特異な女子力を追求している矢口史靖監督の最新作はミュージカル映画。とはいっても、本作は“出演者が突然歌い出すミュージカルへの違和感”を発想の出発点にしているところが矢口流だ。老催眠術師(宝田明)によって、音楽が聴こえるとミュージカルスターになってしまう術をかけられた会社員、鈴木静香(三吉彩花)が、術を解いてもらうために催眠術師を追いかけるロードムービーである。
いままでの「矢口映画」のヒロインの姓はほとんど鈴木で『裸足のピクニック』(1993)は鈴木純子、『ひみつの花園』(1997)は鈴木咲子、『スウィングガールズ』(2004)は鈴木友子といったあんばい。男や家族もそうだ。『アドレナリンドライブ』(1999)は鈴木悟、『ロボジー』(2012)は鈴木重光、『サバイバルファミリー』(2016)は鈴木家の面々。昨今はやりのキラキラネームには目もくれず、主人公たちをごくありふれた名前で統一しているところに矢口流の仕掛けがある。彼の映画の主人公たちはみなありふれていて無個性のようでいて、じつはそれぞれにこだわりをもち、いざとなったらとことん自分の思いや夢を追求するのである。そこから独特の疾走感が生まれる。
 まわりの女子社員に合わせて没個性的に生きていた鈴木静香が、催眠術のせいで、突然、弾けるように歌い踊り出し、人気のエリート社員(三浦貴大)に興味を持たれる。彼のチームにスカウトされたのはいいが、この術を解かないことには正常な(退屈な)会社員生活に戻れない。一週間の休暇を得て、彼女は催眠術師の居所を探す。催眠術師のサクラだった千絵(やしろ優)、居所探しを依頼した私立探偵(ムロツヨシ)、催眠術師に借金を踏み倒された取り立て人たちがもつれながら、名古屋から、新潟、秋田、そして札幌へと日本縦断の旅に出る。このへんは、わくわくする『アドレナリンドライブ』のノリである。
まわりの女子社員に合わせて没個性的に生きていた鈴木静香が、催眠術のせいで、突然、弾けるように歌い踊り出し、人気のエリート社員(三浦貴大)に興味を持たれる。彼のチームにスカウトされたのはいいが、この術を解かないことには正常な(退屈な)会社員生活に戻れない。一週間の休暇を得て、彼女は催眠術師の居所を探す。催眠術師のサクラだった千絵(やしろ優)、居所探しを依頼した私立探偵(ムロツヨシ)、催眠術師に借金を踏み倒された取り立て人たちがもつれながら、名古屋から、新潟、秋田、そして札幌へと日本縦断の旅に出る。このへんは、わくわくする『アドレナリンドライブ』のノリである。
おっちょこちょいで気のいい千絵ともども無一文に等しい旅立ちだったが、きわめてくら~く「年下の男の子」を歌う路上アーティスト、洋子(chay)に駆け寄り、三人で歌い踊れば、これが通行人に大受け。行く先々でどんどんお金がたまり、函館行きのフェリーの料金まで準備できてしまうというのはムシがよすぎるが、気持ちがいいから眼をつぶろう。そもそも荒唐無稽なお話は、ご都合主義とスピードこそ命である。
 会議室でスタートしたミュージカルシーンは工夫に満ちて、さらに次のミュージカルシーンへと続いていく。おしゃれなレストランでの「ハッピーバースデートゥーユー」から「狙いうち」への流れが相当に盛り上がるが、結婚式会場での「ウェディング・ベル」もかなりいい。正常モードから、ふわっと浮くように異常モードに切り変わるわけだが、そこに愛嬌がある。転換点の作り方にセンスがあるのだ。
会議室でスタートしたミュージカルシーンは工夫に満ちて、さらに次のミュージカルシーンへと続いていく。おしゃれなレストランでの「ハッピーバースデートゥーユー」から「狙いうち」への流れが相当に盛り上がるが、結婚式会場での「ウェディング・ベル」もかなりいい。正常モードから、ふわっと浮くように異常モードに切り変わるわけだが、そこに愛嬌がある。転換点の作り方にセンスがあるのだ。
わたしが一番気に入っているのは、駅のチャイムで「浜辺の歌」のメロディーが流れると静香がのびやかな声で歌い出し、それを探偵があっけにとられて見つめるシーンである。チャイムが途切れると静香の歌唱も途切れ、ふと探偵が次の小節を口ずさむとまた彼女の歌唱が始まり、途切れるとまた探偵が口ずさむ。その繰り返しがなんともいえず心に沁みるのである。こうしてふたりの心はひとつに結ばれ、探偵は静香の味方になる。そのなめらかさと自然さは異常さの中でしか生まれない。映画は異常さを作り出す装置になる。
 荒唐無稽な物語であればあるほど、その物語を担うヒロインにはそれ相応の説得力が求められる。異常さを光り輝く奇跡に変える力、生きる歓びに変える力があるかないか。三吉彩花は長い期間、相当な特訓を受けたようだが、その苦労を感じさせない軽やかさにつつまれているのが身上だ。歴代の「矢口映画」のヒロインの中では最も長身で美形といえるが、魅力のポイントは、そのコメディエンヌぶりにある。コメディエンヌというのは、なりふりかまわぬ演技をしながら、自分を高みから冷静に見下ろす理性を備えていなければならない。そうであってこそ、観客は荒唐無稽な物語に入り込むができるのである。
荒唐無稽な物語であればあるほど、その物語を担うヒロインにはそれ相応の説得力が求められる。異常さを光り輝く奇跡に変える力、生きる歓びに変える力があるかないか。三吉彩花は長い期間、相当な特訓を受けたようだが、その苦労を感じさせない軽やかさにつつまれているのが身上だ。歴代の「矢口映画」のヒロインの中では最も長身で美形といえるが、魅力のポイントは、そのコメディエンヌぶりにある。コメディエンヌというのは、なりふりかまわぬ演技をしながら、自分を高みから冷静に見下ろす理性を備えていなければならない。そうであってこそ、観客は荒唐無稽な物語に入り込むができるのである。
さて、静香があやしげな催眠術にかかってしまったのには理由がある。小学生時代の学芸会で主役に選ばれたのはいいが、緊張のあまり歌うどころか吐き気を催し、舞台を台無しにしてしまったのだ。今回の催眠術が結果として立派な心理療法になっている、というのは、催眠術師を演じる名優、宝田明への敬意でもあろう。術を解かれたあとのことは察しがつくだろうが、いったん異常さの中での快楽を知ってしまった者は、もはや正常さという退屈の中には戻れない。催眠術によってミュージカルスターになってしまった静香は、ライトを浴び、人の視線にさらされて歌い踊る人生のスタート地点に立ったことになる。
 だから、この映画はほんのはじまりに過ぎない。はじまりだから未来は見えない。成功するか失敗するか、皆目わからない。だが、とにかく静香は人生の楽しみかたを知ってしまったのである。千絵という確かな“バディ”を見つけてしまったのである。ここで、この道を選ばないということは生きることを放棄するにも等しいのである。静香と千絵に別れを告げ、去って行く探偵が少し寂しそうなのは、もはや自分にはそういう楽しみが持てないということを知っているからである。
だから、この映画はほんのはじまりに過ぎない。はじまりだから未来は見えない。成功するか失敗するか、皆目わからない。だが、とにかく静香は人生の楽しみかたを知ってしまったのである。千絵という確かな“バディ”を見つけてしまったのである。ここで、この道を選ばないということは生きることを放棄するにも等しいのである。静香と千絵に別れを告げ、去って行く探偵が少し寂しそうなのは、もはや自分にはそういう楽しみが持てないということを知っているからである。
平凡な若い女子に焦点をあて、その女子の生きる方向を貪欲に探求するかのような「矢口映画」は今回も立派な青春映画になった。彼の描く青春は、ときに荒唐無稽なようでも、いつも地道な努力をモットーとするきわめて辛口な美学に支えられている。だから「矢口映画」はいつまでも信頼できるのである。
内海陽子プロフィール
 1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
●こちらもご覧下さい
『愛がなんだ』:悲しみとおかしみを包み込む上質なコートのような仕上がり
『バースデー・ワンダーランド』:情感とスピード感に満ちた贅沢なひととき
『家族にサルーテ! イスキア島は大騒動』:けっして自分の生き方を諦めない大人たちを描きぬく
『エリカ38』:浅田美代子が醸し出す途方に暮れた少女のおもかげ
『ファイティング・ダディ 怒りの除雪車』:本作が断然お薦め! 頑固一徹闘うジジイ
『DANCE WITH ME ダンス ウィズ ミー』:正常モードから異常モードへの転換センスのよさ