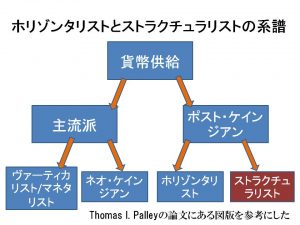熱風がユーモアにつつまれて吹き続ける
『町田くんの世界』(2019・石井裕也監督)
映画評論家・内海陽子
 がんばっているひとや困っているひとを見かけると、すぐに心と身体が動いてしまう町田くん(細田佳央太)。女子図書委員が本を積み上げて運んでいるのを見れば代わりに持ってあげ、壁に張り紙をしようにも高いところに手が届かない男子を見れば肩車をする。すると涼風が吹き、二人の汗ばんだ顔をさわやかにする。その風をわたしも一緒に味わう。誰にでも親切な男子なんて偽善的ではないかと思うひまも与えず、この映画は観客を巻きこむ。誰かを一瞬にして好きになるときと同じように、この映画を好きになる。
がんばっているひとや困っているひとを見かけると、すぐに心と身体が動いてしまう町田くん(細田佳央太)。女子図書委員が本を積み上げて運んでいるのを見れば代わりに持ってあげ、壁に張り紙をしようにも高いところに手が届かない男子を見れば肩車をする。すると涼風が吹き、二人の汗ばんだ顔をさわやかにする。その風をわたしも一緒に味わう。誰にでも親切な男子なんて偽善的ではないかと思うひまも与えず、この映画は観客を巻きこむ。誰かを一瞬にして好きになるときと同じように、この映画を好きになる。
町田くんは、幼いとき井戸に落ちて頭を打ったが、無事救出された。そのときに感じた世の中のひとの善意が彼の世界観を決定的なものにしたようだ。「全人類を家族だと思っている」。斜に構えた同級生・栄りら(前田敦子)がクールに慨嘆するように、町田くんはひとの邪心を疑うことなく善意のかたまりとして生きている。
あるとき、彼は妊娠中の母(松嶋菜々子)がハンバーグを食べたいと言い出したことで頭がいっぱいになり、彫刻刀で指を傷つけてしまう。保健室に行けば不登校ぎみの女子、猪原さん(関水渚)がいて、傷の手当をして自分のハンカチで巻いてくれる。突然の展開に町田くんは不思議な感情に包まれる。だがそれ以上考える習慣のない彼は、猪原さんを大事な同級生のひとりとして強く認識するというレベルにとどまる。
 はたからみればむろん、これは恋の始まり以外のなにものでもなく、栄りらが「普通の恋愛ドラマなら、もう結婚してるよ」と嘲笑う状況にあるにもかかわらず、町田くんは気づかない。猪原さんの屈託ありげな様子に気をもみながらも、その原因が自分にあるとは夢にも思わない。そして、モデルとして活躍する男子、氷室雄(岩田剛典)にフラれた女子、高嶋さくら(高畑充希)を見かければ、ペット飲料を差し出して頭をなでる。また涼風が吹いて彼女の顔をさわやかにする。それが単なる労り以上のものに見えるということを知らない町田くんは、猪原さんがショックを受けたことに気づかない。「もう一度、井戸に落ちろ!」。猪原さんはどんどん不機嫌になっていく。
はたからみればむろん、これは恋の始まり以外のなにものでもなく、栄りらが「普通の恋愛ドラマなら、もう結婚してるよ」と嘲笑う状況にあるにもかかわらず、町田くんは気づかない。猪原さんの屈託ありげな様子に気をもみながらも、その原因が自分にあるとは夢にも思わない。そして、モデルとして活躍する男子、氷室雄(岩田剛典)にフラれた女子、高嶋さくら(高畑充希)を見かければ、ペット飲料を差し出して頭をなでる。また涼風が吹いて彼女の顔をさわやかにする。それが単なる労り以上のものに見えるということを知らない町田くんは、猪原さんがショックを受けたことに気づかない。「もう一度、井戸に落ちろ!」。猪原さんはどんどん不機嫌になっていく。
 関水渚が演じる不機嫌さは、以前に見たことがある、懐かしい表情だと思ったら、石井裕也監督の前作『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(2017)でヒロインを演じた石橋静河の不機嫌さに似ていると気づいた。不機嫌さというのは、一種の感度の良さ、向上心を持ちながらも、それをうまく発揮できない者の焦燥感、の表れと思える場合がある。むやみに不貞腐れている者にはまったく心が動かないが、現状を打破したいという思いを秘めている者は応援したくなる。石井裕也の描く女子の不機嫌さは、いじらしいのである。
関水渚が演じる不機嫌さは、以前に見たことがある、懐かしい表情だと思ったら、石井裕也監督の前作『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』(2017)でヒロインを演じた石橋静河の不機嫌さに似ていると気づいた。不機嫌さというのは、一種の感度の良さ、向上心を持ちながらも、それをうまく発揮できない者の焦燥感、の表れと思える場合がある。むやみに不貞腐れている者にはまったく心が動かないが、現状を打破したいという思いを秘めている者は応援したくなる。石井裕也の描く女子の不機嫌さは、いじらしいのである。
いじらしいと思わせる人間は、みな熱を持っている。だからこの映画は途中から、どんどん熱風を吹き出すようになる。涼風もいいが、熱風はさらにいい。それは人間の思念の熱量が生み出すものだからだ。猪原さんに告白を試みようとした男子、西野亮太(太賀)に対する町田くんと猪原さんの態度は、その典型というべきだろう。熱量と熱量がまっすぐにぶつかりあい、滑稽だけれど独特の情景を生む。
 西野亮太は何を間違えたか、猪原さんへのラブレターを町田くんの靴箱に入れ、それがわかった後は大いに照れながら、町田くんに助勢を頼む。彼のダイレクトな告白にとまどう猪原さんに、町田くんは、西野くんは一生懸命だから、断るにしても一生懸命に断ったほうがいいと言う。三人一緒のデートから猪原さんの決意の言葉まで、一連の流れの中で、三者は三様にすさまじい熱量を放ち、ものごとをぞんざいにしないで生きるとはこういうことだということを突きつけてくる。素晴らしい呼吸のユーモアにつつまれて。
西野亮太は何を間違えたか、猪原さんへのラブレターを町田くんの靴箱に入れ、それがわかった後は大いに照れながら、町田くんに助勢を頼む。彼のダイレクトな告白にとまどう猪原さんに、町田くんは、西野くんは一生懸命だから、断るにしても一生懸命に断ったほうがいいと言う。三人一緒のデートから猪原さんの決意の言葉まで、一連の流れの中で、三者は三様にすさまじい熱量を放ち、ものごとをぞんざいにしないで生きるとはこういうことだということを突きつけてくる。素晴らしい呼吸のユーモアにつつまれて。
さらにいくつものエピソードが織り込まれ、町田くんと猪原さんは「普通の恋愛ドラマなら、もう孫がいるよ」と、栄りらが肩を落とすくらいの仲になっているが、相変わらず町田くんは実直に親切を続け、猪原さんは不機嫌さから解放されることがない。往年のすれ違いメロドラマの変型かと思わせるが、とにかく熱風がユーモアにつつまれて吹き続けるので、わたしは観ていて楽しくてしかたがない。
小さな男の子の手を離れた風船が空を舞い、それをつかまえようとした町田くんがともに空高く舞い出すシーンは、想像や妄想や飛躍という域を大きく超えた、無鉄砲なほどのファンタジー世界だが、不思議に静かなトーンで描かれる。CGテクニックもいささか稚拙で間が抜けていて、町田くんの想念のサイズとよく釣りあっている。肝腎なことは、町田くんが一生懸命に猪原さんを追いかけているということであり、猪原さんが、一生懸命に追いかけてくる町田くんを心待ちにしているということである。
 ふたり一緒に空高く舞いながら、猪原さんが未来への不安を口にしたとき、町田くんが答える。「ゆっくりいこう」。そうだ、それでいい、そうやってお互いをゆっくり見つけて行けばいい。単純で美しい真理を知ったときのような感動を覚える。ひとがひとを思い、痛みに向きあい、やがて全力疾走し、ときには空を舞う。年齢に関係なく、わたしたちはそうやって生きてきたし、これからもそうやって生きて行くのだ。
ふたり一緒に空高く舞いながら、猪原さんが未来への不安を口にしたとき、町田くんが答える。「ゆっくりいこう」。そうだ、それでいい、そうやってお互いをゆっくり見つけて行けばいい。単純で美しい真理を知ったときのような感動を覚える。ひとがひとを思い、痛みに向きあい、やがて全力疾走し、ときには空を舞う。年齢に関係なく、わたしたちはそうやって生きてきたし、これからもそうやって生きて行くのだ。
歳の離れた有能な共演陣が、新人ふたりの同世代を演じ、さりげなく世間並みの賢明さをみせるところに、この映画の深謀遠慮がある。歳を重ねるということは、世間ずれし、世の中をなめてかかるようになることでもある。そのときすでにその人の世界はくすんでいる。しかし、誰もがほんとうは冴え冴えとした世界で生きたいと思っている。自分にとっての宝物を真剣に探し、発見し、磨く意思をもって生きる人たちはつねに気高い。この映画の底に、そういう気高さが小さく光っている。その光りは小さいからこそ貴重なのである。
内海陽子プロフィール
 1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
●こちらもご覧下さい
『愛がなんだ』:悲しみとおかしみを包み込む上質なコートのような仕上がり
『バースデー・ワンダーランド』:情感とスピード感に満ちた贅沢なひととき
『家族にサルーテ! イスキア島は大騒動』:けっして自分の生き方を諦めない大人たちを描きぬく
『エリカ38』:浅田美代子が醸し出す途方に暮れた少女のおもかげ
『ファイティング・ダディ 怒りの除雪車』:本作が断然お薦め! 頑固一徹闘うジジイ
『DANCE WITH ME ダンス ウィズ ミー』:正常モードから異常モードへの転換センスのよさ