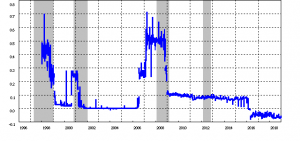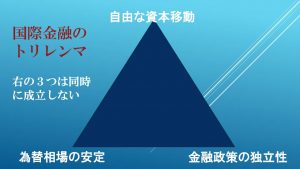常に新鮮で的確な田中圭のリアクション:予想外な純愛の世界
『劇場版おっさんずラブ LOVE or DEAD』(2019・瑠東東一郎監督)
映画評論家・内海陽子
 物語の登場人物が、普段の生活ではまずありえない世界に突入して冒険を繰り広げることを“巻きこまれ型サスペンス”というが、テレビドラマ『おっさんずラブ』も、このジャンルに入れるべき作品かもしれない。どこから見ても同性愛者には見えない主人公(田中圭)が、男らしい上司(吉田鋼太郎)の熱烈求愛に抵抗しきれずに応えてしまい、さらに同僚(林遣都)からの求愛を受け、彼と本気で思い合う仲になる。演じる側も観る側も全く信じていないからこそ、サスペンスになるし、コメディになる。楽しむべきはこのサスペンスを演じる全員のノリのよさと、ふとしたところに見えてくる人間同士のちょっとした真実。立ち止まってその真実を覗きこむと、意外な感動がひそんでいる。
物語の登場人物が、普段の生活ではまずありえない世界に突入して冒険を繰り広げることを“巻きこまれ型サスペンス”というが、テレビドラマ『おっさんずラブ』も、このジャンルに入れるべき作品かもしれない。どこから見ても同性愛者には見えない主人公(田中圭)が、男らしい上司(吉田鋼太郎)の熱烈求愛に抵抗しきれずに応えてしまい、さらに同僚(林遣都)からの求愛を受け、彼と本気で思い合う仲になる。演じる側も観る側も全く信じていないからこそ、サスペンスになるし、コメディになる。楽しむべきはこのサスペンスを演じる全員のノリのよさと、ふとしたところに見えてくる人間同士のちょっとした真実。立ち止まってその真実を覗きこむと、意外な感動がひそんでいる。
 「全く信じていない」と言ったものの、演じる者はやはり、ある一点を信じて演じなければならないだろう。現実の人間の行動というのは、過去を振り返り、未来を予測し、ありとあらゆる利害を一瞬で考えて決定されている。つまり、けっこう不純なものである。だが演じるということは、純真になれるということだ。不純物を払いのけ、人を思うという一点に純真に向きあってみたら、人間の行動範囲はかなり広がり、愛の形も相当広がる。演じる者はそれを演じる。そして『おっさんずラブ』を楽しめるということは、観る者もまた純真な恋愛を信じているということである。純真な恋愛を高みで見て笑いながら、じつは心中ひそかに憧れている、と言い換えてもいいだろう。
「全く信じていない」と言ったものの、演じる者はやはり、ある一点を信じて演じなければならないだろう。現実の人間の行動というのは、過去を振り返り、未来を予測し、ありとあらゆる利害を一瞬で考えて決定されている。つまり、けっこう不純なものである。だが演じるということは、純真になれるということだ。不純物を払いのけ、人を思うという一点に純真に向きあってみたら、人間の行動範囲はかなり広がり、愛の形も相当広がる。演じる者はそれを演じる。そして『おっさんずラブ』を楽しめるということは、観る者もまた純真な恋愛を信じているということである。純真な恋愛を高みで見て笑いながら、じつは心中ひそかに憧れている、と言い換えてもいいだろう。
演じる者と観る者との明らかな相思相愛に支えられてヒットしたに違いないドラマが、堂々映画化されるのは理の当然である。せっかくの大スクリーン、狭い空間での恋の駆け引きやどつきあいばかりでなく、大アクションもご用意してお楽しみいただきます、と言わんばかりの展開で、その意気やよし。田中圭を筆頭に、おなじみのメンバーが元気いっぱいに登場すると、自然に胸が高鳴り笑みがこぼれる。
 春田(田中圭)は上海・香港での転勤生活を終え、恋人、牧(林遣都)へのエンゲージリングを買って帰国した。勤め先の不動産会社営業所では、新しいプロジェクトが始まっており、主導するのは本社の狸穴(沢村一樹)が率いるチームで、牧は本社に異動してその一員になった。かつて春田を口説いた営業部長・黒澤(吉田鋼太郎)は、ちょっとした事故で“春田だけを忘れる”記憶喪失症になってしまった。その結果、一度は身を引いて終わったはずの恋心が新たに芽ばえ、また春田への熱烈なラブ攻勢が始まる。
春田(田中圭)は上海・香港での転勤生活を終え、恋人、牧(林遣都)へのエンゲージリングを買って帰国した。勤め先の不動産会社営業所では、新しいプロジェクトが始まっており、主導するのは本社の狸穴(沢村一樹)が率いるチームで、牧は本社に異動してその一員になった。かつて春田を口説いた営業部長・黒澤(吉田鋼太郎)は、ちょっとした事故で“春田だけを忘れる”記憶喪失症になってしまった。その結果、一度は身を引いて終わったはずの恋心が新たに芽ばえ、また春田への熱烈なラブ攻勢が始まる。
それなりのすれ違いドラマを用意しなければならない、という苦心のほどがよくわかる構成で、まずは牧が春田の浮気(?)を目撃して二人はぎくしゃくし始め、プロジェクトチームの狸穴はどうやら牧にご執心である。また、営業所で春田と新たにコンビを組むことになった山田ジャスティス(志尊淳)は、春田にすっかりなつき、恋の三角関係は入り組んでやっかいな様相を呈するようになる。といっても、どう転んでも深刻な展開になるはずはないので、楽しむべきは個々の俳優の一瞬、一瞬の演技である。
 圧倒的におもしろいのはやはり田中圭で、予想外の出来事やトラブルの際に見せるタイミングのいい顔面の動きは、のびのびと自由自在で多くを語り、しかも鬱陶しいと思わせることがない。常に新鮮で的確、彼のリアクションが相手の俳優を引き立て、さらなるエネルギーを引き出す、といったかんじだ。地上げ交渉に行ったうどん屋で、もみ合いになって粉袋の粉を浴びるシーンや、狭いサウナルームで主要メンバーがひしめいてもみ合うシーンなど、おもてなし痛み入ります、と返すしかないにぎやかさである。
圧倒的におもしろいのはやはり田中圭で、予想外の出来事やトラブルの際に見せるタイミングのいい顔面の動きは、のびのびと自由自在で多くを語り、しかも鬱陶しいと思わせることがない。常に新鮮で的確、彼のリアクションが相手の俳優を引き立て、さらなるエネルギーを引き出す、といったかんじだ。地上げ交渉に行ったうどん屋で、もみ合いになって粉袋の粉を浴びるシーンや、狭いサウナルームで主要メンバーがひしめいてもみ合うシーンなど、おもてなし痛み入ります、と返すしかないにぎやかさである。
くすりと笑わせるのは、春田と牧の性格の違いからくる掛け合いである。大アクションシーンの最中、火に囲まれて身動きが取れなくなったふたりが、一酸化炭素中毒にならないかと心配になるほど長いおしゃべりをする。あげくが「から揚げになるってこういうかんじなのかなあ」と春田が言うと「から揚げではなくて焼き鳥でしょ」と牧が答える。どっちでもいいことを厳密に考え、口にする牧、その反応にいらいらする春田という図が、あちこちにちりばめられて、まさに夫婦漫才の趣だ。
 言うまでもなく吉田鋼太郎も笑いを誘うべく全力投球だ。離婚した妻、蝶子(大塚寧々)と恋中になった部下、栗林(金子大地)と三人で料亭の卓を囲んだ黒澤は、さながら花嫁の父、といった風情で二人の仲を認める。その図そのものがおかしいのだが、吉田鋼太郎はそれをさらに盛り立てる。上司の快諾に調子づき、将来は二人の面倒を見ると豪語する栗林に「立って言うな、座って言え」と絶妙の間合いで言い放つと、おかしさに切なさがほどよく混じり、さすがベテランの芸、と後ろ姿に見入ってしまう。
言うまでもなく吉田鋼太郎も笑いを誘うべく全力投球だ。離婚した妻、蝶子(大塚寧々)と恋中になった部下、栗林(金子大地)と三人で料亭の卓を囲んだ黒澤は、さながら花嫁の父、といった風情で二人の仲を認める。その図そのものがおかしいのだが、吉田鋼太郎はそれをさらに盛り立てる。上司の快諾に調子づき、将来は二人の面倒を見ると豪語する栗林に「立って言うな、座って言え」と絶妙の間合いで言い放つと、おかしさに切なさがほどよく混じり、さすがベテランの芸、と後ろ姿に見入ってしまう。
ところで終盤になると、試写室の同じ列に座った年輩の男性が、随所で「うん」「うん」と小さく声をあげ、からりとした声で笑っているのに気づいた。すっかり『劇場版おっさんずラブ LOVE or DEAD』の世界に入りこんでしまっているようだ。きっと、恋愛に立ち向かう男たちの七転八倒の、純真さそのものに強い共感を覚え、堪能しているのだろう。映画そのものがおおらかに祝福されているようで、くすぐったく快かった。
内海陽子プロフィール
 1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
『愛がなんだ』:悲しみとおかしみを包み込む上質なコートのような仕上がり
『バースデー・ワンダーランド』:情感とスピード感に満ちた贅沢なひととき
『家族にサルーテ! イスキア島は大騒動』:けっして自分の生き方を諦めない大人たちを描きぬく
『エリカ38』:浅田美代子が醸し出す途方に暮れた少女のおもかげ
『ファイティング・ダディ 怒りの除雪車』:本作が断然お薦め! 頑固一徹闘うジジイ
『DANCE WITH ME ダンス ウィズ ミー』:正常モードから異常モードへの転換センスのよさ