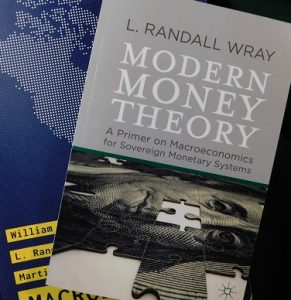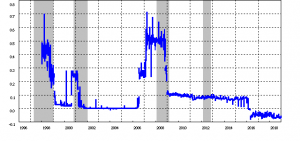RBGがまだ世間知らずだったとき:ルイス・B・ギンズバーグの闘い
『ビリーブ 未来への大逆転』(2018・ミミ・レダー監督)
映画評論家・内海陽子

今年の春、全米にその名を轟かせているルース・ベイダー・ギンズバーグ女史のドキュメンタリー『RBG』(2018・ジュリー・コーエン、ベッツィー・ウェスト監督)を試写室で観た。女性で最長老のアメリカ合衆国最高裁判所判事である、通称“RBG”85歳は、性差別と闘う者たちのスーパーヒーローであり、いまや若者のアイドルでもある。終了後、同世代の女性映画評論家と肩を並べて歩いていたら、彼女が「だらあ~と生きていてはダメねえ」と自嘲気味につぶやいた。わたしも“RBG”の圧倒的迫力に疲れを覚えていたので「そうねえ」と足元を見た。映画についてあれこれ考えるより先に、わが精神のあまりのみすぼらしさに打ちひしがれてしまったのである。
 なにしろ夫と子供がいる身でコロンビア・ロースクールを首席で卒業、以後は女性の権利や、さまざまな性差別と闘う弁護士として活躍し始めるのである。家事、育児、仕事の準備で眠る暇もないのは当然で、遊びごと以外で徹夜した記憶のないわたしなどは、ただあっけに取られてしまうというか、怠慢さを叱りとばされているような気持ちになる。いや、ちょっとひがみが過ぎて口が滑った。彼女は心から法律を愛しているのであり、その法律を正しいものにしたいという情熱にかられているだけなのである。
なにしろ夫と子供がいる身でコロンビア・ロースクールを首席で卒業、以後は女性の権利や、さまざまな性差別と闘う弁護士として活躍し始めるのである。家事、育児、仕事の準備で眠る暇もないのは当然で、遊びごと以外で徹夜した記憶のないわたしなどは、ただあっけに取られてしまうというか、怠慢さを叱りとばされているような気持ちになる。いや、ちょっとひがみが過ぎて口が滑った。彼女は心から法律を愛しているのであり、その法律を正しいものにしたいという情熱にかられているだけなのである。
 小柄な身体を意識してか、がっしりしたメガネをかけ、ファッションに気を配り、装身具はやや華美である。物腰は洗練されているが、長年の頭脳労働と裁判闘争の結果なのかどうか、風貌は猛禽類を思わせるものになっている。おだやかで人あたりのいい老婦人、という概念から最も遠いところにいるかんじだ。そして、どことなくさらし者になっている自分を熟知して受け入れ、愛想とユーモアを忘れずに取材や催しにつきあうのである。充実しているだろうが、特殊な孤独をかかえているようにも見える。
小柄な身体を意識してか、がっしりしたメガネをかけ、ファッションに気を配り、装身具はやや華美である。物腰は洗練されているが、長年の頭脳労働と裁判闘争の結果なのかどうか、風貌は猛禽類を思わせるものになっている。おだやかで人あたりのいい老婦人、という概念から最も遠いところにいるかんじだ。そして、どことなくさらし者になっている自分を熟知して受け入れ、愛想とユーモアを忘れずに取材や催しにつきあうのである。充実しているだろうが、特殊な孤独をかかえているようにも見える。

手の出しようがないなと思っていたら、見逃していた『ビリーブ 未来への大逆転』(2018・ミミ・レダー監督)がDVDで観られることになった。これは、学生結婚した“RBG”が一女をもうけて間もない、ハーバード・ロースクール入学のころから始まる伝記映画である。演じる女優、フェリシティ・ジョーンズが親しみやすく可愛いので、画面が明るくとっつきやすい。職人肌の映画監督ミミ・レダーは、広範囲の人が共感を覚えやすいようにと考えたようで、あくまでやわらかいイメージを作りだす。この映画のヒロインは“RBG”ではなく、まだ世間知らずのルースである。

1950年代。ルース(フェリシティ・ジョーンズ)は女性、母親、ユダヤ系、という弱点の持ち主である。法律の勉強をしているといやおうなく、女性蔑視の発言を浴びせられる。彼女を育てた賢明な母親からは「淑女であれ」「自立せよ」「感情的になるな」と教えこまれたが、守り抜くのはなかなか難しい。だがなにより幸運なことに夫が頼りになる。夫マーティ(アーミー・ハマー)は頭がよくて努力家のルースを認め、協力を惜しまない。料理の腕は彼女より上なので、自然に彼の担当になった。ルースはマーティがガンに倒れたときには彼を支え、ハーバードでは、夫のほうの講義にも出てノートを取る。負けてなるものか。

ルースは激しいといってもいいほど向学心に燃えている。けれども髪を振り乱したり、服装が乱れたりすることはない。子育てにも真剣に取り組み、娘が少し大きくなれば仕事の席にも同行させる。1970年代になり、彼女は大学教授として活躍しているが、弁護士になる夢を諦めきれず、ある訴訟の弁護を買って出る。それは、独身男性が母親の介護をすると、法的な優遇措置を受けられないという問題の訴訟である。彼女は男性もまた差別されている実態を知る。マーティは「男も男らしさに縛られている」と説く。

ドキュメンタリー『RBG 最強の85才』より
女性が無鉄砲な発言や行動ができるようになった世代の娘ジェーン(ケイリー・スピーニー)が、できのいいルースに食ってかかるシーンや、逆にルースを励ますシーンがあるが、ドキュメンタリー『RBG』のほうにはそういうわかりやすい母娘愛のようなものは感じられない。おそらく実際は、家族一丸となってルースを畏怖したのではないかと思う。初老になった娘ジェーンと息子ジェームズの姿や応答には、すぐれているが特殊な母を持った子供たちの「やれやれ」感がにじんでいる。
酒に例えると『RBG』が大辛口なら『ビリーブ 未来への大逆転』は中甘口というところである。フェリシティ・ジョーンズは口元にメイクをほどこし、巧みに若かりし頃の可愛いルースになり、働きながら子育てをする現代の女性にも励ましになるようなキャラクターを作りあげている。しかしエンディング、長い石段を上がるブルーのドレスのルースの後姿を引き継いで、現在の本物の“RBG”が同じく冴えたブルーのドレス姿で現れると、わたしは思わず身が引き締まる。というよりも、じつは身がすくむのである。平凡な女の娘に生まれてよかった、という思いがこみ上げる。こういう感慨も一種の差別意識なのだろうか。
内海陽子プロフィール
 1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
1950年、東京都台東区生まれ。都立白鷗高校卒業後、三菱石油、百貨店松屋で事務職に従事。休みの日はほぼすべて映画鑑賞に費やす年月を経て、映画雑誌「キネマ旬報」に声をかけられ、1977年、「ニッポン個性派時代」というインタビューページのライターのひとりとしてスタート。この連載は同誌の読者賞を受賞し、「シネマ個性派ランド」(共著)として刊行された。1978年ころから、映画評論家として仕事を始めて現在に至る。(著者の新刊が出ました)
『愛がなんだ』:悲しみとおかしみを包み込む上質なコートのような仕上がり
『バースデー・ワンダーランド』:情感とスピード感に満ちた贅沢なひととき
『家族にサルーテ! イスキア島は大騒動』:けっして自分の生き方を諦めない大人たちを描きぬく
『エリカ38』:浅田美代子が醸し出す途方に暮れた少女のおもかげ
『ファイティング・ダディ 怒りの除雪車』:本作が断然お薦め! 頑固一徹闘うジジイ
『DANCE WITH ME ダンス ウィズ ミー』:正常モードから異常モードへの転換センスのよさ